|
今二つの松竹映画が話題となって時代劇ブームとなっている。ひとつは藤沢周平原作、山田洋次監督の『たそがれ清兵衛』、もうひとつは浅田次郎原作、滝田洋二郎監督の『壬生義士伝』である。このふたつの映画は共に主人公の心とその行動が、見る者の心を揺さぶって涙を誘うのである。主人公に共通するのは貧しさである。この時代はほとんどの人が貧しかったが、貧しいなりにも差はある。懸命に愛するもののために働かねばならない。侍であれば、働くことは時には戦って相手を斬らねばならぬこと。上の命令は絶対である。
|

岩手山と一本桜
(壬生義士伝のパンフレットから) |

雫石の家 |
何故今このような映画が作られるのか?制作者が訴えたいものは何なのか?時代はともに江戸末期、背景はまるで違うが、現代日本に置き換えて訴えたいものがあるはずだ。そしてそれがヒットするということは、制作者の意図が観衆の心の琴線を捉えたのである。

『たそがれ清兵衛』PRホームページより転載
江戸末期、庄内の平侍・井口清兵衛は、労咳を患った妻の死後、娘2人と老いた母親をなんとか養い暮らしている。仕事が終わると同僚との付き合いを断って帰るため、仲間には「たそがれ」と呼ばれていた。ある夜清兵衛は、久しぶりに再会した幼なじみの朋江を家に送った際、朋江が離縁した男に果し合いを申し渡され、木刀で打ち負かしてしまう。噂はたちまち城中に広まり、朋江も清兵衛に心を砕いていく。その頃、藩主の死により城は揺れ始めていた。
山田洋次監督が描く日本人の心は、他のどんな映画よりも心の溝を突いてくる。その監督が、時代小説の匠・藤沢周平の小説を映画化した本作は、時代の波、運命の波を静かに見つめる侍魂を情感豊かに描いたヒューマン時代劇だ。貧しさのなかで、清兵衛は常に冷静に世の中を見渡し、へらず口をたたかず、自分の芯を貫いていく。
一方で、思い切って朋江に結婚を申し込む清兵衛のかたくなな表情や、意に反する藩命に向かっていく凛とした態度は、侍の心意気を見せられるよう。そして、注目すべきは果し合いシーンの見事さだ。張り詰めた緊張と気を抜いた会話の波が起こすリアルな「間」と、急に顔色を変える余吾の不気味な迫力が一対一の殺陣を盛り上げる。

『壬生義士伝』PRホームページより転載
混迷する現代社会の汚れや悲しみをすべて洗い流してくれるような、美しくかつ力強い感動作が誕生した。誰もが生きている限り、自分の胸に幾度となく問いかける言葉がある。「人はいったい何のために生きているのか?」『壬生義士伝』は、その問いに一点の曇りもない瞳で答えられる男の物語だ。
その男、名は吉村貫一郎。幕末の混乱期に、尊皇攘夷の名のもと、京都府中守護の名目で結成された新選組の隊士である。幕府の力が弱まるにつれ、明日をも知れない運命に翻弄される隊士たちの中で、貫一郎はただ一人、異彩を放っていた。名誉を重んじ、死を恐れない武士の世界において、彼は生き残りたいと熱望し、金銭を得るために戦った。全ては故郷の妻と子供たちを守るためだった。
大義名分、権力、名誉。そんなものはどうでもよかった。愚直なまでに「愛する者のために生きる」。家族だけではない。友、仲間、心を通わせた相手のために貫一郎は生き抜いた。やがて「守銭奴」と彼をさげすんでいた隊士も気づき始める。この男の「義」は、「人としての愛」なのだと。
波瀾の運命をたどりながらも、この見事なまでに純粋な生き方と出会う時、私たちはただ「まっすぐに泣く」ことでしか、この感動を表現することはできない。

さて、何故これらの映画がヒットするのか?何が観衆の心の琴線を捉えたのか?
共通するのは『愛』だ。
愛する者のために戦うのはカッコイイが、主人公たちはそのために戦っているのではない。これがポイントだ。
我が家族が少しでも貧しい生活から逃れられるよう、一家の大黒柱は働かねばならぬ。「頑張れ!」と言われて頑張るのではなく、ただただ妻子のために働くのである。純粋なまでにそのために。他に何の邪心も無く。
ただし世は民主社会にあらず、奉公は主のため、命令は絶対である。
生きるためには他人を殺しても良いのか?
YesもNoもない。
ひるがえって現代。伸び盛りの日本で、突き進めば成果を得てきた団塊の世代が定年を目前にリストラの嵐に見舞われている。するほうもされるほうも同じ世代だ。弱肉強食、真夜中に帰宅してはため息をつく。仕方がないんだ、中国の「貧しい」ひとたちが豊かになる過程で先行した日本が追い上げられる。かつては欧米に対して今の中国が日本だった。
しかし、オヤジさん、現実を肯定して諦めていいのか?貴方の妻子はどうするんだ?家族のためにあんたはいったい何をしてるんだ?かつての日本の家庭は、オヤジを上座に妻子や父母が食卓を囲んで3世代が同居して、まず手をあわせて今日の糧を与えて頂いたことに感謝して食事を始めた。冬の朝食の木の床の冷たかったこと!今考えればよくもまあ。おふくろさんは食材をやりくりして何とかして食卓を賑やかにしようとした。肉や魚は盆、正月以外は滅多に出ない。ベジタリアン?贅沢言うんじゃない!祖父も祖母も自分のできることで家計の助けになるよう努力し、子供たちも父母を手伝って働いた。それでも食えない場合、子供を奉公に出す、あるいは売る。非情な親と言えるだろうか?深沢七郎の楢山節考では家族のために老婆が山(姥捨山…クリック)で死のうとする。老いた母を背負った息子が涙をボロボロこぼしながら山道を登る。生のなかに死がきざし、死のなかに生を宿すことは、あたりまえ過ぎるほど当たり前なことだった。山形からいかだ舟で下る「おしん」、母も父も張り裂ける胸の中で「すまん、おしん、許してくれ」、それがついこの前の世の中だった。
今企業の中にあって働く我々はどうなのか?家族のために努力しているのは間違い無い。しかしたそがれ清兵衛の生き方ができるか?たそがれている者はたくさんいるだろう。しかし彼の凛とした生き方を真似できるお父さんは少ないだろう。仕事は仕事、しかしまず家族のために。グチを言ったり、弱音を吐いたり、赤提灯でぶつぶつ言っていないで、家庭で身体一杯の愛を注ぐ。
岩手の寒村、雫石の貧しい吉村貫一郎は、南部藩のあてがい扶持では食って行けぬ。京都へ出稼ぎに行く。仕事は人斬りだ。斬った相手にも家族がいる。愛する妻子もいるかもしれぬ。しかし彼は斬らねばならぬ。鬼の形相で金を数える。仲間の遊び、飲酒の誘いにも乗らずひたすら金を貯める姿が、ヒトとは思えぬ空恐ろしさとともに「守銭奴」のそしりを受ける。最後は、「生きたい、家族の元へ帰りたい」と念じつつも、自らの命を絶たねばならぬ無念が伝わってきて涙を禁じ得ない。ついこの前まで、出稼ぎしなければ食って行けないのが雫石では当たり前だった。
さて、こうして見てくるとこの2作品がヒットするのは、「ついこの前までは当たり前だった」世界と現代の余りにも大きいギャップ、ついこの前の世界を児童体験として持っている団塊の世代の郷愁、核家族となって姨捨山の代りに老人ホームへ父母を送るうしろめたさと主人公のりりしい生き方、これらがないまぜとなって、『自分には今できないけれども本来そうであるべきもの』の姿が見事なまでに描かれているからであろう。しかし自分にはできない。そうしたい、せねばならぬ。家族への愛とともに仕事における筋の通った生き方が共感を呼ぶ。
壬生義士伝では吉村貫一郎の子を背負った商人が新潟への道すがら、わざわざ北上川にかかる夕顔瀬橋まで戻ってページトップの岩手山を見せながら、「お坊ちゃん、この山をよ〜く見てくなんせ、この川をよ〜く見てくなんせ、これがお坊ちゃんのふるさとでやんすよ」と言う。石川啄木や宮澤賢治はじめ岩手の盛岡とその近辺に育ったものにとって、この山川は心の拠り処である。
そしてよく出てくる言葉「おもさげねがんす」、これは美しい。申し訳ありません、申す訳ねぇなはん、おもさげねがんす、段々美しくなる。
(2003年1月20日)
|
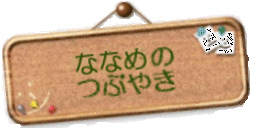
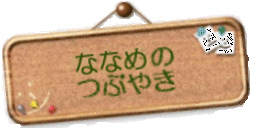
![]()